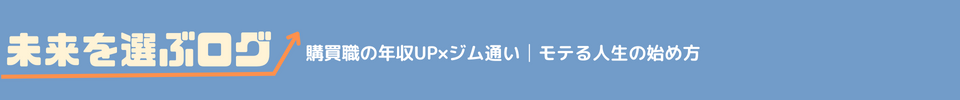購買・資材調達部員の海外調達方法と注意点を知りたいですか?
・海外調達が大事なことは分かるけど、始め方が分からないよ?
・どんな基準で海外調達に踏み切ればいいのだろう?
・海外調達はどんなポイントに注意すべきなの?
上記の疑問を解決します。
・海外調達の目的
・海外調達に踏み切る判断の基準
・海外調達のメリットとリスク
・失敗しない海外調達の始め方
・海外調達での失敗談
資材調達の仕事を始めて25年になるボクも、最初に海外調達を始めたのは10年前には海外取引のしくみが分からず苦労しました。
「安いから」という理由だけで海外調達に踏み切るのはリスクが高すぎます。
資材調達部員が安易に回りに流されると、会社に損失を与えてしまいますからね。
優秀な資材調達部員は、海外調達で正しい判断ができなければなりません。
では、海外調達に取り組む新人バイヤー向けにポイントとリスクを解説します。
海外調達の5つの注意点│資材調達部長が解説するポイントとリスク
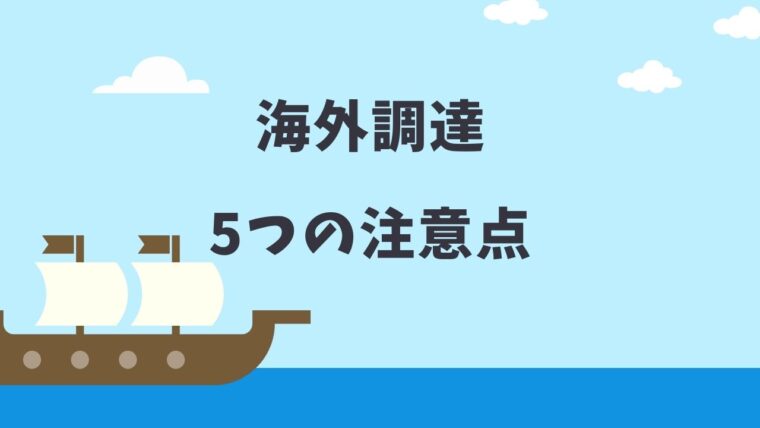
「海外調達の比率を上げるべき」と言われ始めたのは2010年ごろ。円高が進み1ドル100円を切ると、会社から「海外調達の指令」が出るようになりましたね。
海外調達が必要になる3つの理由は以下のとおり。
①コストメリット
②海外にしかない技術
③リスク分散(国内供給の不安)
対して海外調達のリスクは以下の3点です。
①為替・税法・関税
②言語・文化・時差
③距離・輸送・ロット
海外調達には「輸入が必要な理由」と「リスク」があるから、資材調達部員はこの点をふまえて海外調達を検討しなければなりません。
海外調達リスクを帳消しにするコストメリット基準
海外調達を行う一番の目的は「コストメリットの実現」です。
経験上、リスクを帳消しにするコストメリットの基準は20%以上です。
20%以上のコストメリットがある場合、海外調達の以下のリスクを許容できます。
・為替リスク
・在庫増加のリスク
・関税費用
海外調達に踏み切る場合は、価格が20%以上安価なことを基準としましょう。
また、海外からしか調達できない場合は選択肢が無いため、なるべく有利に購買できる方法を探します。
・直接取引ができないか
・優良な商社(エージェント)を探す
・海外で競合できないか
上記を検討してリスクを分散します。
海外調達の5つの注意点
1、海外調達でしか手に入らない
2、コストが20%以上安価
この2つの場合に「さあ海外調達をしよう!」となるわけですが、注意すべきポイントは「国内との違い」です。
5つの注意点は以下のとおり。
① 輸送コスト(Ex・FOB・CIF)
② 習慣の違い
③ 調達リードタイムとロットサイズ
④ 契約条件
⑤ トータルコスト
順番に解説します。
① 輸送コスト(EX、FOB、CIFの違い)
海外の見積もりでは、通常輸送コストが別となっています。
「見積もりのときに、輸送費を見逃して結局高くついてしまった……」
輸送費は大きな経費のひとつですから、初めての海外調達でも上記のミスは許されません。
海外取引ではIncoterms(インコタームズ)という取引条件の統一規格があります。
取引条件ではこの国際ルールが適用されます。
どこの時点までが取引先の責任範囲なのか?によって輸送コストが変わります。
・Ex-factory│工場出荷まで
・FOB-Free On board│甲板渡し:荷積みされるまで
・CFR-Cost And Freight│運賃込み:指定の港まで
・CIF-Cost Indurance and Freight│運賃保険料込み:指定の場所につくまで
見積もり段階で、以下の事は確認しておきましょう。
・自社責任の輸送はどこからなのか?
・自社責任の輸送費にどれだけかかるのか?
・保険料金はいくらかかるのか?
② 習慣の違い
日本での当たり前は海外では通用しません。
日本の取引先と同じに考えていると、思わぬトラブルを引き起こすことがあります。
現地の情報は事前に把握する必要があり、例えば、わたしの失敗例は以下のとおり。
・インドネシア(イスラム圏)では断食月があります
・中国やベトナム、韓国では旧暦のお盆、正月が休みになります
・フランスではバケーションの習慣があります
・アメリカでは収穫祭や、クリスマス休暇があります
・国によってはストライキで業務が止まります
習慣を確認しておくことで避けられるトラブルばかりですから、事前確認は超重要です。
③ 調達リードタイムとロットサイズ
海外調達では国内よりも輸送に時間がかかるし、一回のロットサイズも大きくなります。
海外が安い理由の一つは「大量生産」だということを忘れてはいけません。
・輸送の長さ
・ロットサイズの大きさ
この点を考えずに、見た目の安さだけに囚われると、在庫のコストを見逃します。
注意点②であげた、海外特有の休暇や、ストライキの影響によって、輸送のリードタイムは思った以上にかかりますよ。
例えば、ボクも以下のような経験があります。
・季節風が強いという理由で飛行機が何日も飛ばない
・台風の影響で港に何日も入れない
・通関がストライキで荷物が来ない
・日本の空港が大雨で水浸しになり荷出しができない
海外調達では、「まさか!」というような出来事も起こりますから、リスクを考慮すると、安全在庫がどうしても増えます。
リスクにあわせた在庫コストはいくらになるのか?は事前に把握しておきましょう。
④ 契約条件
日本では、当たり前に行われる商慣習でも、海外ではまったく異なりますから、契約内容はよく確認しておきましょう。
揉めやすいポイントをあげておきます。
・支払い条件
・不具合時の処置方法
・先行情報の取り扱い
事前確認が必要なポイントは以下のとおり。
・支払いは、いつの時点を起算して、いつまでの期日なのか?
・不具合品が発生した場合、対応はどうなるのか?
・先行情報で資材を準備するのか?
例えば、
・見積もり条件が工場出荷時のEx-Factry
・輸送は海上輸送で行う
・出荷時点から数えて60日後に入金
となっていたとします。
その場合、現物がまだ到着していなくても、代金を支払わなければなりません。
日本だと、物が入って受け入れ検査が合格したものにお金を払いますよね。
海外では出荷した時点で支払いが発生します。
もし品物に不具合があったとき、海外では次のような対応になります。
・その分のマイナス伝票を切る(Cregit)
・代納はなし(買い手が新たな注文をする)
また、購入品を作るための素材の注文書を要求される場合もあります。
特にアメリカでは、エンロン社の不正会計事件からSOX法というものが存在します。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
このために、注文書の無い手配をしてもらえません。
日本のように、先行情報で事前に準備するという概念が存在しないから、どんなに未来の納期でも、注文書を発行する必要があります。
先行で確定注文を行うことはリスクしかありませんよね。
どうしてもの時は、先の顧客との間にも確定注文や引取り保証を確約しておくなど、自社のリスクを最小限にする手をうっておきましょう。
⑤ トータルコスト
「トータルで安いのか?高いのか?」結局はこの点に集約されます。
追加で注意すべき点は、輸入に関わる以下の3つのコストです。
・為替の変動リスク
・梱包仕様
・国内費用
為替の変動は予測できません。
リスクを下げるなら、ドル建てで支払いを行えば問題ありません。
梱包仕様については、こちらが明示しても守られないこともあります。
また、輸送業者が開封⇒再梱包したり、取り扱いの破損も日常茶飯事ですよ。
以下は、うちの新人がよくやるミスです。
・破損のリスクを改善するうちに、当初見積もりよりも過剰梱包となる
・安全な輸送業者に変更して、いつのまにかコストアップになっている
・購入量が減り、海上輸送よりもエア輸送のほうが安くなるが、気がつかない
また、国内費用も見落としがちなコストです。
・国内通関費用
・荷おろし(デバンニング)費用
・書類作成費用
・保険料
知っていれば、事前に確認できるコストですよね。
そのほかにも
・相手国の代理店との取引なのか
・相手国のメーカーとの直接取引なのか
・日本の商社を仲介する取引なのか
・海外進出している日本メーカーなのか
・材料を日本から支給するのか、現地調達なのか
など、確認すべきポイントはまだまだあります。
海外調達の本を1冊手元に置いておくとミスが減らせます。
おすすめは日経文庫ビジュアルの「貿易・為替の基本」です。
コンパクトな本のわりに内容は十分、ビジュアル解説付きでお手軽に確認できますよ。
※amazonの中古で1円で買える本です。
海外調達の失敗談:輸入貨物への課税
海外調達をしていると「輸入関税」という税金が発生します。
5年に一回程度、税務調査が入ることがあり、税金の知識がないと修正申告や、最悪の場合は脱税扱いになってしまうから注意が必要です。
輸入に対する課税価格は以下の2つです。
- 現実支払価格
- 加算要素
現実支払価格は「インボイス(仕入書)」の価格なので、問題ないですが、加算要素は見落としやすいから、注意が必要です。
加算要素の代表例は以下の5つです。
- 輸入港までの運賃等(FOBやEXWのとき)
- 買い手から負担される費用(エージェント手数料など)
- 無償支給品(原材料、梱包資材、工具、設計費など)
- ロイヤルティやライセンス料金(著作権や特許権など)
- 売り手の収益(スクラップなど)
上記はインボイスに乗らないため、輸入関税の申告漏れを起こしやすいから注意が必要です。
一方で、申告後に発生した費用や、消費税は修正申告で返還される場合があります。
- CIF以外の契約で発生した輸送費
- 返品で過剰に支払った消費税や関税
例えば、金型を中国で生産し、不具合で修正のために返品した場合、消費税がその都度かかりますが、修正申告をしておけば、後日返還されます。
まとめ
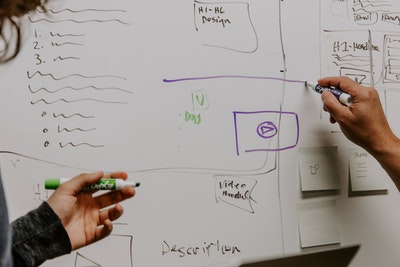
ここまで読んできたあなたは
・海外調達ってややこしいな……
・リスクが高そうだしやだな……
こんな風に思ったかもしれませんね。
ですが「海外調達比率○%」のように、会社からの指示が出ることもあります。
そんなときに、正確な判断ができる人が優秀な資材調達部員です。
最後に、海外調達を成功させるポイントをまとめておきます。
・海外調達のトータルメリットを判断する
・事前のトラブル予測と対策をしておく
・相手先との意思疎通を確実にしておく
・その国の習慣や法律を理解して対応する
・スタートしてから起こるトラブルを地道につぶしていく
・調達が安定化したら、再標準化(ルールの見直し)をする
海外調達の最大の目的はコストメリットの実現です。
資材調達部員が判断を間違えると、逆に高い買い物をすることになってしまいますが、トータルコストの比較をしっかりしていけば大きな失敗は予防できます。
海外調達スキルは資材調達のスキルマップでも重要なスキルの一つです。ボクの失敗を参考にしつつ、あなたのスキルがあがって、年収アップにつながると嬉しいです。

では、本記事は以上です。