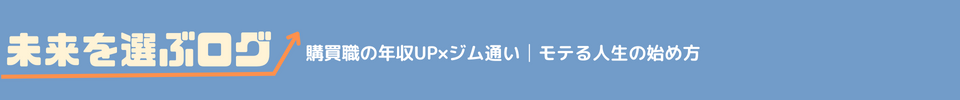こんな疑問を解決します。
・資材部・購買部・調達部の違い│調達は機能です
・資材部・購買部・調達部の業務内容の違い
・就職、転職時のミスマッチを予防できる
「資材」「購買」「調達」は同じような使われ方をするので、社会人でも正しい定義が分かる人は少ないです。
この記事では資材購買歴25年の購買部長が正しい定義をまとめてみました。
就職活動では正しい定義が分かっていないと、エントリーしてイザ面接となったときに「思ってたのと違う!」となるかもしれません。
就職活動は就職活動は情報戦だから、ムダにできる時間はありません。
・この会社は部署ごとに分業しているのか?
・志望する部署の募集なのか?そうではないのか?
・向いてない部署に配属される可能性は無いのか?
上記のことが事前にわかるだけで、就職活動を効率化できますよね。
とはいえ、上記のことを調べても就活に成功できるわけではありません。
悲しい現実ですが、本記事では現役部長で採用責任者でもあり筆者が、理由も解説していきます。
購買と調達の違いは機能です│会社の規模によって担当範囲が変わるだけ
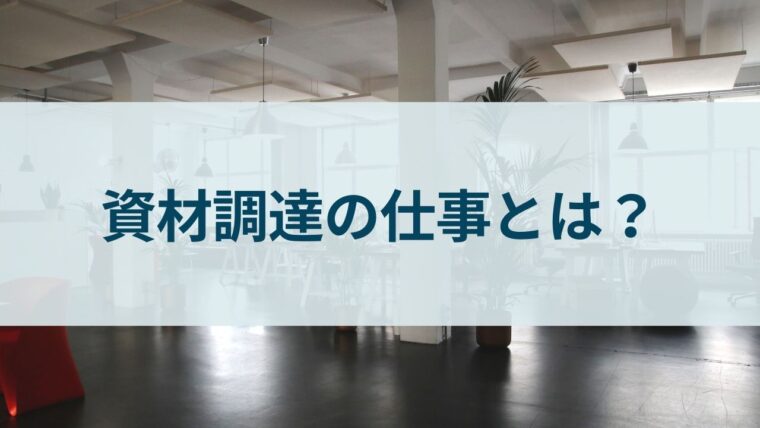
結論から。
「資材部」は材料などの高額品だけを「調達」する部署
「購買部」は文房具も含めたすべてのものを「調達」する部署
「調達」は「資材部」「購買部」の機能のひとつです。
なお、正式なJIS(日本工業規格)での「購買」の定義は以下のとおり。
生産活動に当たって、外部から適正な品質の資材を必要量だけ、必要な時期までに経済的に調達するための手段の体系
引用元:JIS(日本工業規格)
調達は資材購買の「業務」の中の「機能」の一つ
資材購買の業務の中に4つの機能があり、そのうちのひとつが「調達」の機能です。
資材購買の4つの機能は下表のとおり。
1.契約機能
2.調達機能
3.在庫管理機能
4.開発購買機能
上記の機能を仕事の流れに当てはめていくと「資材部」「購買部」「調達部」の仕事内容が理解できます。
順番に解説します。
資材購買業務の流れと機能
購買の機能を業務別にまとめました。
| 資材購買の機能 | 購買業務の流れ |
| 1、契約機能 | ①見積書を入手する ②見積価格の検討評価 ③購入先の決定 |
| 2、調達機能 | ④注文書の作成・送付 ⑤納期管理 ⑥検収・受入れ検査 |
| 3、在庫管理機能 | ⑦入庫処理 ⑧在庫管理 ⑨出庫処理 |
| 4、開発購買機能 | ⑩新規取引先の開発 |
表の内容を解説しますね。資材購買の基本的な業務の流れは以下です。
① 見積書を入手する
② 見積価格の検討評価
③ 購入先の決定
④ 注文書の作成・送付
⑤ 納期管理
⑥ 検収・受入れ検査
⑦ 入庫処理
⑧ 在庫管理
⑨ 出庫処理
⑩ 新規取引先の開発
上記を機能に分類すると以下のとおり。
①~③が「契約機能」
④~⑥が「調達機能」
⑦~⑨が「資材管理機能」
⑩が「開発購買機能」
順番に解説します。
①~③:資材購買の「契約機能」
契約は取引先と価格を決定するまでの業務です。
資材購買の機能の中でも、わりとスキルが求められる業務になります。
▼契約担当の主な機能と役割
- 原材料、部品を購入できる取引先を複数見つける
- 見積書を取る
- 見積価格の評価する
- 条件や価格の交渉をし、納期を確認する
- 購入予定価格と納期が合致すれば取引先として決定する
- 注文書(契約書)を作成し送付する
注文書を発行送付すれば契約業務は終わりです。
次からは調達担当の業務範囲です。
⑤~⑥:資材購買の「調達機能」
調達は納期を確認し、納期までに入手する役割を持っています。
比較的誰にもできるマックジョブです。
▼調達担当の主な機能と役割
- 入手可能日を確認する
- もし、日程に問題があれば、その問題の解決策を検討
- 関連部門に依頼し、問題の解決のために提案や交渉をする
- 最終の納期を確定する
- 当初の日程に変更があれば関係部署に連絡する
納期通りに納品されたら、次は資材管理の業務範囲になります。
⑦~⑨:資材購買の「在庫管理機能」
資材管理は、納入された原材料を受領→検収→保管→工場へ出庫する役割を持っています。
この仕事も新入社員に任されやすいです。
▼材料管理担当の主な機能と役割
- 納入日に受領、検収する
- 受入れ検査をする
- 検査合格を確認して、材料倉庫に入庫処理をする
- 材料倉庫にて保管
- 製造日程に合わせて使用する原材料を準備する
- 指定する部門に出庫する
材料管理部門は、新入社員が最初に配属される部署として最適です。
なぜなら、社内で使用する原材料の種類やその量を現物で確認できるからです。
そして、入庫や出庫を通じて、関係者とのコミニュケーションをとることもできるので、人間関係の構築にも役に立ちます。
このときに良い関係を築いておくと、将来、調達や契約の業務を行う際に役に立ちます。
⑩:資材購買の開発購買機能
開発購買は新しく企画される新製品にかかわる機能です。
・必要な新技術、新工法
・新技術や工法を有する取引先を見つけ出す
・情報を製造部門や設計開発部門へ提供
・新取引先を評価し、契約する
製造業では常に新製品を企画検討しています。
新製品には、他社に負けない新しい機能や特徴を追加する工夫が必要ですよね。
そんな新しい情報を社内に供給できる仕事が「開発購買」です。
▼開発購買担当の主な機能・役割
- 新技術・新工法、新規取引先などの情報収集
- 新製品に応じて工場部門、開発設計部門への情報提供
- 新規取引先に関する評価と採用の決定
この業務には経験豊富で技術に詳しい人材が必要です。
この仕事を極めると、定年を待たずにコンサルタントとして独立も可能です。
会社の規模による担当範囲の違い
企業の規模によって機能を分業するか?専任するか?の違いがあります。
・大企業では機能別に4つの課や係に分けています。
・小規模の企業では、すべての業務を一人で行なっています。
理由は、大企業ほど調達する原材料の種類や数量が多く、ひとつの部署では処理できないからです。
もっともポピュラーなのは「契約」と「調達」の仕事を同じ担当者で行なう形態です。
スキルがいる業務とそうではない業務に分けられる
企業では資材購買の仕事は次の2つに分業されます。
A:交渉などのスキルを必要とする業務
B:指示された仕事や決められた仕事をする簡単な業務
① 見積書を入手する
② 見積価格の検討評価
③ 購入先の決定
④ 注文書の作成・送付
⑤ 納期管理
⑥ 検収・受入れ検査
⑦ 入庫処理
⑧ 在庫管理
⑨ 出庫処理
⑩ 新規取引先の開発
新人のうちは比較的簡単なB(④⑤⑥)の仕事を任されることが多いと思います。
何年か実力をつけていくとA(①②③)の仕事ができるようになり楽しくなっていきます。
さらに管理職になって、⑩の仕事ができるようになると「資材購買最高!」となります。
こうなると、資材購買はとても魅力のある仕事になりますよ。
身につけてきたスキルによっては、コンサルタントとして起業独立も可能です。
購買職はスペシャリストを目指せる仕事

キャリア25年のボクの結論は、調達は文系でも将来的にスキルが蓄積できるため、やりがいがある仕事です。
さらに、サラリーマンに向いていない性格のボクでも力を発揮することができる唯一の仕事。
これからの未来は「第4次産業革命が進み、テック系の理系エンジニアしか職がなくなる」言われています。
しかし、資材購買マンを目指しておけば、テック系エンジニア人材に匹敵するスキルを身に付けることができるから、文系には特におすすめです。
まとめ
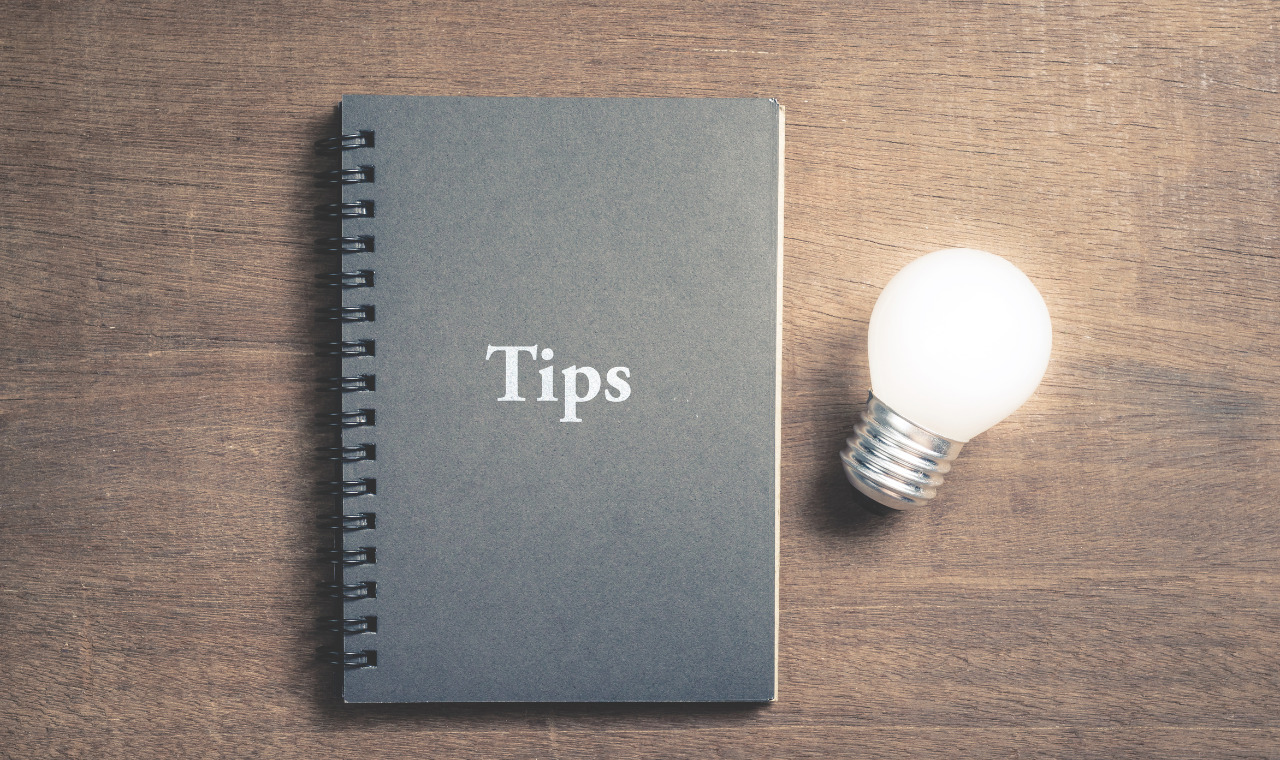
資材購買マンを目指す際には「資材、調達、購買の違い」が分かると、求人の見極めができます。
とはいえ「資材、調達、購買の違い」をいくら知っていても採用が有利になるわけではないですよね。
なぜなら「調達」は「機能」に過ぎないからです。資材・購買の仕事の「機能」をいくら知っていても意味がありません。
「採用」で大切なことは、あなたが「どんな性格なのか」「何ができるか?」「どんなスキルを持っているか」です。
結局のところ、就職活動は「あなたと企業のマッチング」をする作業だから「採用」が欲しければ、まずはその部分を検索するべきですよね。
「初めての就職活動でそんなことわからないよ!」かもですが、就職活動で差がつくのって、そういったリサーチ能力の部分です。
あなたと企業のマッチングを見極める具体的な手順は、以下の記事で解説していますので、参考にしつつ、ぜひ「採用」を勝ち取ってください。
新卒の就職手順を知りたい方
≫【保存版】調達購買職への就職手順│スケジュールごとのポイントまとめ
転職手順を知りたい方
≫【未経験者向け】購買転職手順の完全講義│現役部長が求人の見方を解説
キャリアに不安がある方
≫【解決策あり】30代でも購買転職の書類選考に受からない3つの理由
ということで、本記事は以上です。